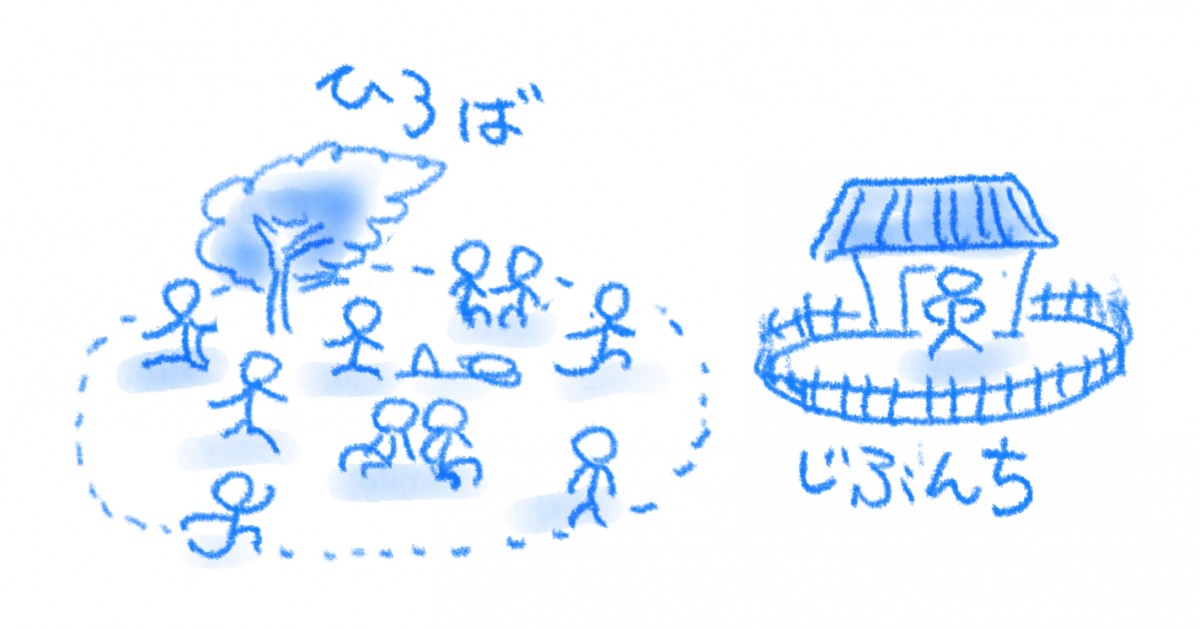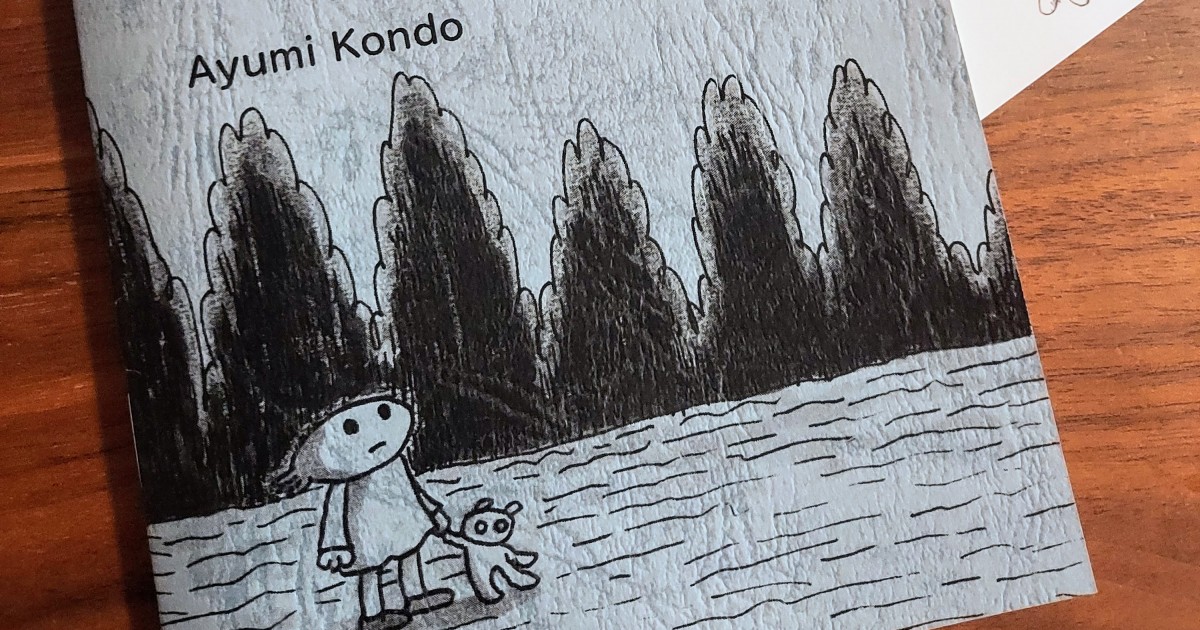★12月の沖縄にて。【vol.25】
那覇市壺屋
「桜がひとつだけ咲いてるよ」
やちむん通りを歩き始めた途端、右手の坂道を下ってきたおじさんにいきなりそう声をかけられた。濃いまゆ濃いまつげに黒目がちの大きな目。ウチナーンチュである。
「桜がね、ひとつだけ咲いてる」
「うそ!?」
私は反射的にそうリアクションして、指差しながら元きた坂道を登り始めるおじさんについて行った。夫も後に続く。
東京なら見ず知らずの人に路上で話しかけられてそのままついていくことなど起こり得ないけど、沖縄だとこういうことがままある。単に私の警戒心のなさかもしれないが、おじさんの発するうちなーイントネーションは何とも柔らかく可愛く聞こえるので仕方ない(?)。
沖縄では2月頃にやんばるから桜が咲く。といっても本土のうす淡いソメイヨシノではなく、寒緋桜という濃いピンクの桜だ。
でも12月初旬の那覇じゃさすがにまだ早すぎでは?と思いながら、鮮やかなピンクに彩られた木が一本だけ現れることを期待しながら歩いた。
おじさんは坂道の左側にある、四畳半ほどしかない空き地に踏み込み、植え込みのあいだを進む。進むったって猫の額ほどの狭さでその先は行き止まりだ。鮮やかなピンクの木などどこにもない。えっ、この人どこに連れてく気??と訝しんだ瞬間、「ここ見てごらん」。
頭を低くして枝々の中に突っ込むようにして、おじさんが指さした箇所を見る。たった一輪、小さな小さなピンクの花が開きかけていた。
「ひとつだけ」って一本じゃなくてたった一輪だったの!?しかもこんなに奥の奥にひっそり咲いてたなんて!!
私「ほんとだ桜だっ!」
夫「…よくこんなの見つけたね??」
おじさん、ちょっと得意げである。ほんとになぜこんな小さな開花を発見したんだろう。毎日チェックしてるんだろうか。おじさんはその隣の木々を指差しまくる。「そこにね、サンニン、月桃があるよ。これはほら、パパイヤさー」
小さな空き地に、バラエティ豊かな沖縄の植物が共存してる。
「こっちはシークヮーサーね」
とはいえ実はひとつもなっていない。「葉っぱまけてごらん、まけて嗅いでごらん」とおじさんは言う。
「まけて」が何か分からず、葉に鼻を近づけても何も分からない。おじさんが何度も「まけないと分からないよ」と言う。アッ「曲げて」と言ってくれてるのか!と気づき、葉っぱの真ん中をパキッと折ってから嗅いでみる。するとあら不思議!はっきりしたシークヮーサーの香りが立ちのぼってきたではないか。すごいすごいと盛り上がる私である。
おじさんは次々と説明を始める。あっちの塀のうえ見てごらん、島とうがらしがあるでしょ。ほら、まだ青いやつだよ。朝のドラマに出てきたがじゅまるもあるよ…。
なるほど、おじさんは本土からの観光客のために分かりやすく沖縄の木や花を紹介してくれているのだ。
気をつけて帰るんだよ、ウンありがとー!と手を振りあって別れたあと、おじさんは再び坂を下ってやちむんのお店の前にたたずみ、次に話しかける観光客を探しているようだった。ただ、小さな空き地に咲く一輪の桜と、沖縄の植物の存在を教えるために。
夫「近所の人なのかなあ」
私「…いや、多分あれは壺屋の妖精。というか沖縄の草花をつかさどる精だよ」
沖縄に行ったらあなたも出会うかもしれない。その時はスルーせずぜひお話を聞いてほしい。

読谷村波平
読谷に宿をとって10年以上経つというのに、私たちは「チビチリガマ」を知らなかった。
沖縄に興味を持ったきっかけは幼少期に読んだ灰谷健次郎「太陽の子」ということもあり、沖縄戦のことは色々学んだし、旅では観光より戦跡を優先してきたつもりだ。でもそれは南部に集中する有名な場所を巡っていただけなのだ。
読谷で行きつけのスーパーからすぐのところにチビチリガマはあった。
(ガマというのは天然の鍾乳洞。戦時には沖縄じゅうのガマを防空壕として、住民や日本兵が避難していた)
大きな看板があるわけでもなく、ただ歩道の横に色あせた「チビチリガマ見学者の皆さんへ」という注意書きがあるのみ。Googleマップの画像がなければ入口すら分からなかっただろう。鬱蒼とした木々のあいだに、急な階段が下にのびている。
こわごわ降りていくと広い空間に出る。天井は濃い緑。眼の前には大きな鍾乳洞が真っ黒な口をあけている。そこかしこに立つ石像がこちらを見ている。空は快晴なのにここは薄暗くひんやりとしている。これまで見たどの戦跡よりもリアルに「当時」が迫ってくる気がして怖ろしかった。
このチビチリガマは、避難していた140人の住民のうち83人が集団自決をしたことで知られる場所だ。日本軍の「米兵に捕まったら殺されるぞ」という言葉や「生きて虜囚の辱めを受けず」という教えのために、米軍からの投降の呼びかけには応じないまま住民同士がお互いを殺し合うという凄惨な結末になったという。
私と夫はただただ、頭を垂れて一心に祈るしかなかった。
すぐ近くにはシムクガマというのがあり、そこにも多数の住民が避難していたそうだ。チビチリガマを経た米軍はここにも到達、同じように投降を呼びかけたがやはり応じる者がいなかった。壕内には「自決しよう」の空気が漂う。
しかしハワイからの帰国者である比嘉兄弟が「アメリカは(住民は)殺さないよ」と皆を説得し、外にいる米兵と対話。結果的に集団自決を回避し、約1000人もの住民を救ったそうだ。
「情報や知識を得ているかどうか」の違いだとは、とても軽々しく言えない。
「こうなったらこうなる」「この場ではこうあるべきだ」という情報やこころざしは、いとも簡単に操作されたり歪んで醸造されたりする。それはいきなりではなく、少しずつ少しずつずらされて、慣らされていく。潮流や意気を操るのが得意な為政者とそれに従順な民が揃えば、現代であっても「まさかありえない」というような道に突っ走る可能性は大だし、自分や他人の命を粗末にする結末にも充分なり得る。
1000人のただなかで「いや待て、やめよう」と言える冷静さと勇気を持つひとになれるかどうか。そのひとの後に続けるかどうか。沖縄から帰ってからも、そのことを考えている。

すでに登録済みの方は こちら